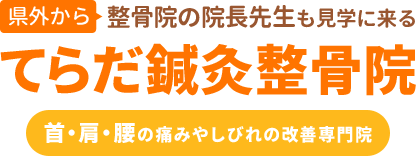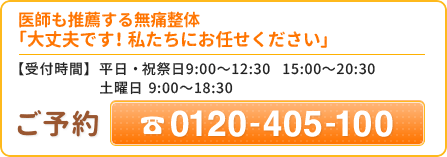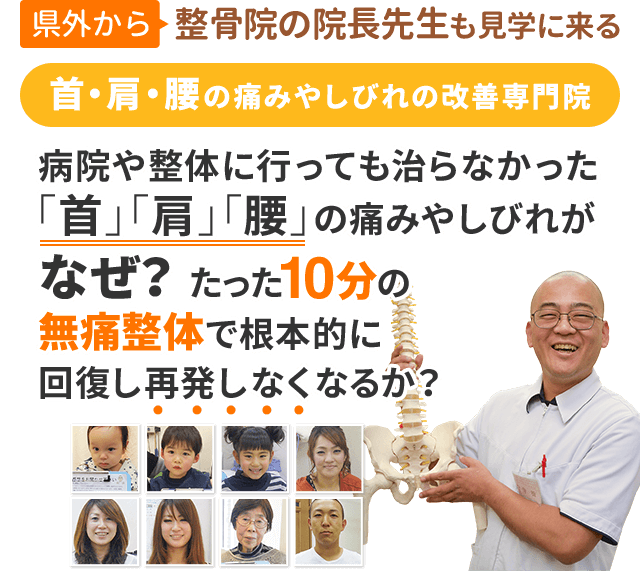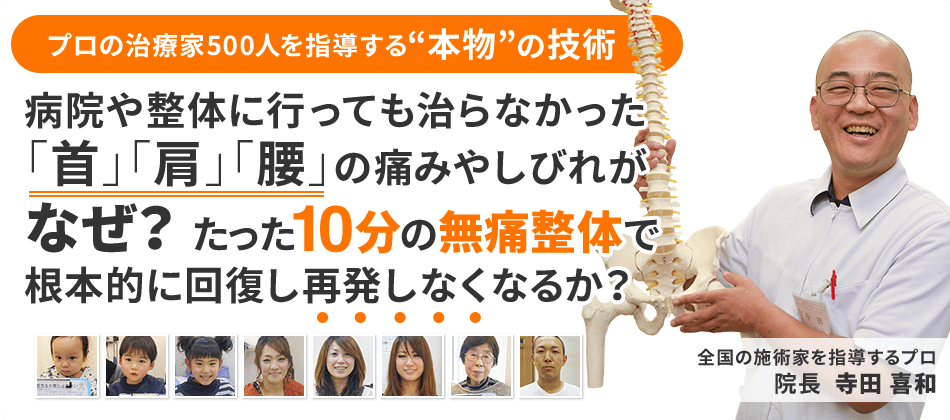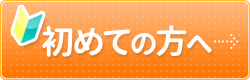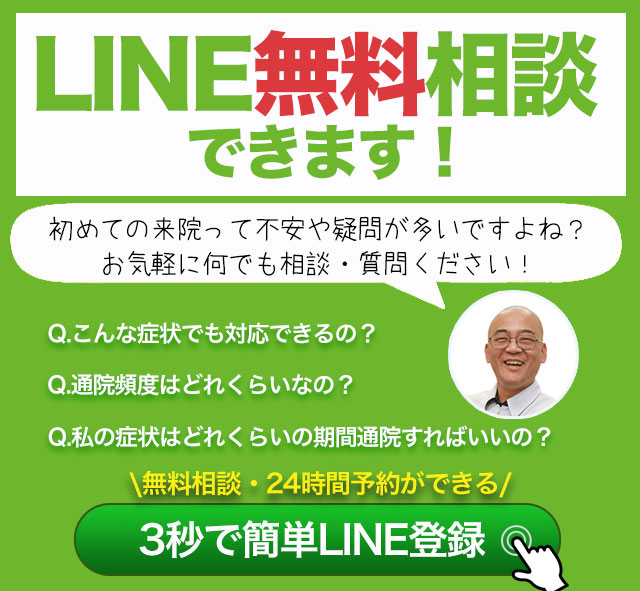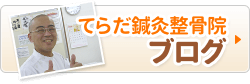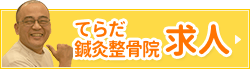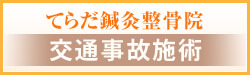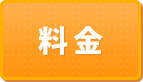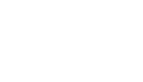2015年11月25日 : 未分類
脊椎(せきつい)分離症は、成長期のスポーツを習慣的に行う子供にしばしばみられる背骨(せぼね)の病気です。発症したばかりのときに治療を開始すれば、完治する可能性が高いため早期発見・治療が望まれます。
分離症を改善するための治療についてお伝えします。
1.分離症の病期分類とは?
治療を開始するまえに、病気分類を評価する必要があります。ほとんどの病気に対して病期分類が用いられていますが、病期とは病気の進行具合を示しており、治療計画や今後の経過を予想するうえで非常に重要な指標となります。
分離症の病期評価には、画像検査が行われます。
レントゲンを行えば、腰椎分離症や腰椎すべり症を診断することは可能です。レントゲンでは分離した部分が黒く抜けて、スコッチテリアの首輪に見えることがあり、「スコッチテリアサイン」と名前がついています。
しかし、より詳細に病気の進行度を判定するために、通常はCTやMRI検査が行われます。とくに脊髄の圧迫が疑われる場合はMRIが必要であり、症状が似ている若年性ヘルニアとの鑑別にも有用です。
分離症は様々な分類法がありますが、「西良による分類」では、CTとMRIの検査の結果をもとに、病期を「早期」「初期」「進行期」「偽関節期」に分類しています。
このほかCT所見での分類では、CTでHair line (髪の毛のような黒く細いライン)を認めれば「早期」、Clear gap(明確な分離)を認めれば「進行期」、さらにくっきりと分離して時間が経過した状態は「終末期」と表現され、分離した部分が偽関節に至った状態を示しています。
2.分離症にはどんな治療があるの?
どの病期であっても、まずは手術を行わない保存療法が基本です。コルセットによる体幹の固定や疼痛に関する薬物療法が主流です。
スポーツによる過度の負荷が原因なので、まずはスポーツをお休みすることが重要です。それに加え、子供の成長期腰椎分離症では、発症の「早期」であれば、数ヶ月~半年ほどのコルセット着用で分離した部分の骨癒合(こつゆごう)が期待できます。
骨癒合とは分離した骨がふたたびくっつくことです。適切な早期の治療で約9割に近い骨癒合が期待できると言われています。画像などで、分離部分の安定性や骨癒合の完成度を評価しながらコルセット治療を終了する時期を検討します。
この時に用いるコルセットは、市販のコルセットではなく、患者さんの腰のにあったオーダーメイドの医療用コルセットです。軟性コルセットと硬性コルセットがあります。
軟性コルセットはしっかりした支柱が入っており、市販の簡易コルセットよりも固定力が高くなります。「進行期」以降では硬性コルセットが主に用いられます。プラスチックや金属の支柱が使われており、固定力はコルセットの中でも最強です。市販のコルセットでは効果が確認されていないので注意が必要です。
また、成人の場合でも、コルセット使用により、腰の動きを制限し、腰を使う動作のときに分離した部分への負荷を軽くして、腰痛を予防・軽減する効果があります。
通常、お腹の筋肉である腹横筋がお腹を前から後ろに向かって抑えてくれることで腰にかかる負担が減るのですが、コルセットはこの腹横筋の役目を助ける働きがあるため腰痛が改善するのです。
3.すべり症を予防するために
脊椎と脊椎の間には椎間板(ついかんばん)があります。若年では、椎間板と脊椎の間にはやわらかい成長軟骨があり、分離症があると不安定な脊椎を支えきれずに、上下の椎骨がずれる「すべり症」が起こりやすくなります。
分離症自体は男児に多く、発症頻度は女児の約2倍ですが、ひとたび分離症を起こすと、女児の方が男児よりも2倍、すべり症を起こしやすいという報告があります。
すべり症をおこすと、腰痛やしびれ・筋力低下といった神経根症状が現れる可能性が高くなるため、すべり症への進展を予防することが重要です。
特に骨年齢が幼若な小学生の場合ではすべり症のリスクが高いため、いずれの病期においてもすべり症への進行を予防するために、スポーツを中止して、コルセットによる固定を行うことが多いです。
高校生以降になると、成長軟骨は骨に置きかわり、上下の脊椎どうしの固定力が高まるため、すべり症がおこりにくくなります。
4.その他の治療
腰椎分離症のリハビリテショーンとして、腰椎を安定させるために、腰部と骨盤の筋肉を強化する体操と筋肉を伸ばすストレッチを行います。自己流ではなく、医師やリハビリの先生と相談して、正しい運動を行うことが大切です。
この運動は、スポーツを中止している間も行います。また、治療が終わってからも継続することが大切です。
疼痛がある場合は、経口内服薬の鎮痛薬を使用しますが、それでも症状が改善しない場合は神経ブロックを行うことがあります。
さらに、分離症が進展して、分離すべり症となり、下肢の痛みや筋力低下などの神経症状がある場合や、スポーツ選手として今後もスポーツを続けたい場合など、症状や本人の希望を考慮して手術が選択されることがあります。
2015年11月25日 : 未分類
分離症とは、スポーツを習慣的に行う子供に多い「成長期腰椎分離症」を指すことが多く、背骨の病気の一つです。分離症には特徴的な症状があり、その症状で分離症を疑い、さらに画像検査所見により確定診断されます。子供の一番近くにいる存在である、親や、スポーツを指導する大人が分離症の症状を理解し、子供の症状を見逃さないことが大事です。
今回は、腰椎分離症の症状について詳しくお話しします。
1.特徴的な腰痛の症状とは?
分離症は、第5腰椎に最も頻度が高く、繰り返す機械的な負荷が原因で生じる疲労骨折であり、運動時の腰痛が主な症状です。
発症の仕方は様々で、徐々に痛みが出てくるケースや、ある時突然ギクッと痛みが走ってその後腰痛が持続するという場合もあります。
その中でも分離症に見られ、医学的に有意とされている所見は、以下の3つがあります。簡単な身体検査なので、セルフチェックも可能です。
1:Kemp徴候
2:腰椎伸展時痛
3:棘突起(きょくとっき)叩打痛・圧痛
これらについて一つずつ詳しく解説します。
2.Kemp徴候とは
座った状態またはまっすぐ立った状態で、やや斜め後ろに腰椎を倒して、回旋します。左右どちらも行います。その時に、右または左に回旋した時に痛みを生じた側が病側となります。
これは、脊髄からでた枝である神経根が圧迫されるためで、この検査で腰痛が誘発されることを「Kemp徴候」といいます。
成長期のスポーツを行う若者がKemp徴候を認めた場合、画像所見で実際に分離症と診断された人は約7割であり、非常に感度の高い所見です。一方で、Kemp徴候が陰性で、画像所見で分離症ではないことが証明されたのは約半分でした。
このことから、Kemp徴候を認めた人は、分離症を積極的に疑い画像検査をする必要があります。さらに、この徴候は分離したばかりの発症早期に約8割の人に認められ、偽関節期まで進行すると約3割と減少します。
また、陰性でも約半分の人が分離症であったことから、陰性の場合でも、腰に負担のかかるスポーツ歴や好発年齢(12~17歳が約9割)などから分離症が疑わしい場合はさらなる検査が検討されるべきです。
腰椎分離症は無症状の患者も多いのですが、腰痛が発生する機序については十分に解明されていません。自覚症状がない場合でも、長時間の立ち仕事や腰を反らせたり横に曲げたりする時のみに腰痛を生じることがあります。
3.腰椎伸展時痛とは?
立った状態で前かがみになると腰痛が出現することを「腰椎伸展時痛」といいます。
腰部伸展時痛があるスポーツを習慣的に行っている若者10~18歳では、約半数に腰椎伸展時痛を認めています。
この腰椎伸展時痛に関しても、病期が進行するにつれて頻度が減少し、早期では約9割ですが偽関節期には約6割と報告されています。
4.棘突起(きょくとっき)の圧痛とは?
棘突起とは椎骨の後端が隆起して突出した構造であり、背骨として体表から触れることができる。
腰椎分離症は第5腰椎に発生することが多いため、この部位の棘突起を押す、もしくは軽く叩くと痛み(棘突起叩打痛)を生じることがあります。分離症の約6割に認められ、発症早期であるほど陽性率が高くなります。
5.複数の所見で感度がアップ
これまでに、Kemp徴候、腰伸展時の痛みと棘突起に限局した圧痛の3つをご紹介しましたが、複数の所見がそろうほど分離症の可能性が高くなります。
発育期のスポーツ選手での発症頻度は約40%と効率であり、偽関節に至る例も多いことから、スポーツを定期的に行う子供に腰痛を認めた場合は、簡単にできるこれらの所見を確かめてみるのも良いかもしれません。
6.早期に発見する利点
発症早期ほどいずれの所見も感度が高く、この時期に医療機関を受診して分離症を見つけてもらうことが大事です。
発症早期にスポーツを中止して、コルセットにより体幹固定を行うことにより分離した骨が再度くっつく骨癒合(こつゆごう)偽関節期になると、骨癒合は期待できません。
7.すべり症の症状とは
高校生頃までは、椎骨の一部がやわらかい成長軟骨で構成されているため力学的に弱く、分離症と気付かずにスポーツで負荷をかけ続けることで、分離症が伸展して「分離すべり症」になることがあります。
すべり症とは、分離症で上下の椎骨の固定が不安定であるために、椎骨が前方にすべってしまう病気です。前後にずれた椎骨が神経を圧迫すると、下肢のしびれや疼痛、下肢の筋力低下といった神経症状が出現することがあります。
また、脊髄からでた枝である神経根(しんけいこん)を圧迫すると、おしり、太ももの後ろ、すねや足先などにしびれや痛みを生じることがあり、座骨(ざこつ)神経痛様の症状を示すことがあります。
若いほどすべり症の発症頻度が高くなり、スポーツを継続することが困難となり、またコルセットなどの保存療法では改善しないために手術が必要となるケースもあります。
将来スポーツ選手になりたいという子供の夢を叶えるためにも、早期に分離症の治療を行い、このすべり症への進展を防いであげることが非常に大切なのです。
2015年11月25日 : 未分類
分離症は、スポーツを行う子供が、腰の曲げ伸ばしやひねり運動を繰り返すことで背骨に負担がかかり、疲労骨折することにより起こる病気です。骨折なので、早めに発見すれば折れた骨を再度くっつけることが可能であり、分離症の原因を知ることで早めの対策をとることができます。
今回は、そのほとんどが成長期の子供にみられる分離症の原因についてお話しします。
1.生まれたての赤ちゃんは分離症がない?
昔から、分離症は小児期~高校生までのスポーツをほぼ毎日行う子供に多く認められ、年齢が増すにつれて発生頻度が増加することがわかっていました。
そこで、問題となるのは、生まれつきの素因である「先天性(せんてんせい)」の病気なのか、生まれたあとに要因がある「後天性(こうてんせい)」の病気かということでした。両者では治療法が大きく異なる可能性があるからです。
調査の結果、二足歩行ができない胎児や新生児では分離症を認めないことが明らかになりました。このことから、分離症のほとんどが生まれつき発生しているのではなく、主にスポーツによる反復的な力学的負荷という後天的な原因で発生していると考えられました。
2.生まれ持った素因も関与
しかし、人種的に発生率が異なり、二分脊椎といった椎弓や椎体の形態異常がある人に多くみられ、兄弟姉妹といった家族間で発生する傾向も認められることから、分離症を起こしやすい先天的な形態的異常があると考えられています。
このことから、分離症は、先天的になりやすい素質の上に、後天的な要素であるスポーツによる負荷が加わることで発生すると推定されています。
3.腰椎に多い分離症
発生する部位は、5つある腰椎のうち一番下にある第5腰椎に多い(約90%)ことがわかっています。立った状態では、第5腰椎とその下の仙骨(せんこつ)の間で上半身の重さを支えており、一番負荷がかかりやすくなります。
画像技術の進歩により、スポーツによる力学的な負荷の画像解析調査が可能となりました。調査では、体を反らす動き(伸展運動)やねじる運動(回旋運動)が繰り返しおこなわれることで、第5腰椎の椎間関節周囲に力学的な負荷がかかって椎弓(ついきゅう)と呼ばれる椎骨から背中側に突き出た突起が、疲労骨折を起こすことがわかりました。
さらに詳しく説明すると、腰を反らす伸展運動では、椎弓をせん断(はさみでものを切る時のちから)するような伸展ストレスが働きます。そして、腰をねじる回旋運動では、椎弓を上下別方向へ回旋させるストレスが働きます。
伸展と回旋という2つのストレスが反復することで、腰椎の椎弓の下の部分から徐々に亀裂が生じます。そして、何度もストレスが加わることで完全に分断し、時間がたつと、完全に分離した骨同士が関節のような働きをするため、「偽関節」と言われます。
椎骨周囲にはたくさんの神経が走っており、また、骨膜にも痛みを感じる神経があるため、亀裂がはいった発症早期には痛みが強く現れることが多いです。
テニス、ラグビー、サッカー、野球、バスケットボール、器械体操、フィギュアスケートなど、ほとんどのスポーツが、腰の伸展運動や回旋運動を要します。
このため、分離症発症の際には、スポーツを一時的に中止して、コルセットを用いて腰の伸展ストレスや回旋ストレスを軽減することが重要となります。
4.なぜ大人に少ないのか
日本では、人口の約6%、700万人程度が分離症であると予測されています。男女別では男性が女性の倍で、男性に多い疾患です。
また、ほとんどの分離症発症時期は10~17歳ころまでの発育期で、成人になってからの発症は極めてまれです。18歳以降になると、椎骨がしっかり骨化して硬くなるため、起こしにくくなります。
どの国でも、有名なスポーツ選手は幼少時から厳しいトレーニングを積んでいます。成長期の子供の骨はしっかり骨化しておらず、大人よりも細く弱いため、腰の回旋や伸展のストレスに耐え切れずに骨折すると考えられています。
腰痛をもつ若いスポーツ選手の多くが分離症を発症していると言われており、運動時の症状がひどいため、手術を要する、あるいは選手生命をたたれることもあります。子供のスポーツ教育をサポートする大人が正しい知識をもち、子供達に安全にスポーツを行ってもらうことが大切です。
5.なぜ分離すべり症なるのか?
分離症がさらに伸展すると、上下の椎骨固定が不安定であることから、椎骨が前後にすべる「すべり症」になります。
子供では、椎骨がまだ完全に硬い骨ではなく、成長軟骨という柔らかい骨で一部が形成されているため、その部分が力学的に弱いことが原因です。
幼いほど、骨が未熟であるため、すべり症合併は、幼いほど発生率が高くなります。このため、たとえ偽関節期という病態が進行した状態であっても、すべり症を予防するためにコルセットで体幹固定を行うことがあります。
6.高齢者の分離すべり症
高齢者では、骨密度の低下や、椎骨と椎骨の間にある椎間板(ついかんばん)の変性により、椎骨が不安定になり、椎骨が前後にすべる「すべり症」と、さらに椎弓が骨折する「分離症」を合併する「分離すべり症」を起こすことがあります。
2015年11月25日 : 未分類
脊椎(せきつい)分離症とは、腰痛持ちのスポーツを習慣的に行っている子供にしばしばみられる病気です。早く発見できれば、脊椎すべり症への進展を防ぎ、手術をせずに治療できる可能性も高くなることから、早めの診断・治療が望まれます。
1.脊椎分離症ってどんな病気?
脊椎とは、背骨(せぼね)を形成する一つ一つの骨のことを指します。背骨は、頚椎(けいつい)7個、胸椎(きょうつい)12個、腰椎(ようつい)5個、仙椎(せんつい)5個がひとかたまりになった仙骨(せんこつ)、尾骨(びつい)3~6個の計約30個の脊椎から構成されています。
脊椎分離症は、ほぼ腰椎に起こるため、分離症といえば「腰椎分離症」を指すことが多く、5つの腰椎の中でも仙骨に近い、下位腰椎(特に上から数えて5番目の第5腰椎)に多く認めます。
脊椎には「椎弓(ついきゅう)」という弓状に飛び出た突起があります。椎弓は、上の脊椎と下の脊椎とをしっかり固定する上関節突起と下関節突起の間を橋渡ししており、脊椎にとって非常に重要な構造の一つです。この椎弓が分離した状態が、「脊椎分離症」です。
2.子供に多い分離症
子供の背骨はまだ柔らかいため、スポーツなどで過剰に負荷がかかると力学的に弱い部分がすることがあります。
腰痛を持つスポーツ選手を対象とした調査では、16~40%(研究によって差があります)が腰椎分離症であり、腰痛を持つ18歳以下の若者でも約16%に腰椎分離症を認めた、という報告があります。
さらに、腰を伸展させた時に痛みがあり、ほぼ毎日スポーツをしている10歳~18歳の若者では、なんと、約半数に腰椎分離症を認める結果となりました。
このことから、10~18歳の発育期に習慣的にスポーツを行っている子供は非常にリスクが高いことがわかります。
3.子供以外に分離症は起こるのか?
諸説ありますが、基本的に椎弓のみが外傷で損傷をうける可能性は低く、年齢とともに頻度が増加する傾向も認めていません。特に、骨がしっかり形作られる高校生以降での分離症発症は、非常にまれです。
高齢者では椎骨が前後にすべる「すべり症」と合併する、「分離すべり症」を認めることがあります。
4.遺伝との関係は?
腰椎分離症は家族内での発生例が多いため、遺伝的素因が一因と考えられています。
椎体や椎弓の形態異常、あるいは二分脊椎などの脊椎の病気を合併しているケースも見受けられ、兄弟姉妹で分離症を発症した例も多く報告されています。
こういった遺伝的、体質的な要素にスポーツによる過度の力学的負担が加わって疲労骨折が起こるのではないか、という説が有力です。
5.子供でのすべり症合併
すべり症とは、上下の脊椎が前後にずれる状態のことです。分離症によって起こる「分離すべり症」と、分離をともなわない「変性すべり症」に大きく分けられます。ここでは、分離すべり症についてお話しします。
上下の脊椎の間には椎間板(ついかんばん)という繊維とコラーゲンでできたクッションがあります。脊椎と椎間板の間には、成長軟骨が存在し、高校生頃までに硬い骨に置き換わります(骨化)。
子供の場合、分離症によって上下がぐらぐらで不安定になった骨を、柔らかい成長軟骨が支えきれずに上下の脊椎がずれてしまい、「分離すべり症」となります。
6.分離症をもった人が中高齢になったら?
分離症を持つ子供が中高齢になると、脊椎と脊椎との間のクッションの役割を果たす椎間板のコラーゲンが失われて椎間板が硬くなり、椎間板が変性することですべり症を合併することがあります。
すべり症合併例の多くは神経を圧迫して、腰痛と神経根刺激症状(しびれ、筋力低下)が出現します。
7.早めの診断・治療が大切
治療の基本は、手術を行わない保存療法です。保存法には2種類あり、分離した骨を再びくっつける「骨癒合(こつゆごう)」を目指す治療と、「疼痛コントロール」のための治療です。
発症早期であれば、運動の中止と分離症治療用のコルセットを用いることで、分離した部位の骨癒合(こつゆごう)が期待できます。通常数ヶ月~半年の治療が必要となります。
若年であるほど、成長軟骨が柔らかく、すべり症を合併しやすいため、進行度に関わらず、コルセットの治療を行われることが多いです。
しかし、激しい運動をしなければ無症状であることも多いため、受診したときには完全に分離しており、分離した部分が関節のようになる、「偽関節」の状態であることも多いのが現状です。この場合は、骨癒合は困難であるため、疼痛コントロールに主眼がおかれます。
病態が進行して痛みが強い場合やスポーツ活動を今後も継続するために、腰椎分離すべり症に対して脊椎固定術という手術が行われることがあります。こうなる前、つまり骨癒合が期待できる時期に、早めに診断、治療してあげることが重要なのです。
2015年11月25日 : 未分類
脊椎(せきつい)分離症とは、腰痛持ちのスポーツを習慣的に行っている子供にしばしばみられる病気です。早く発見できれば、脊椎すべり症への進展を防ぎ、手術をせずに治療できる可能性も高くなることから、早めの診断・治療が望まれます。
今回は、「脊椎分離症になる傾向があるのはどんな人?」をテーマにお話しします。
1.脊椎分離症ってどんな病気?
脊椎とは、背骨(せぼね)を形成する一つ一つの骨のことを指します。背骨は、頚椎(けいつい)7個、胸椎(きょうつい)12個、腰椎(ようつい)5個、仙椎(せんつい)5個がひとかたまりになった仙骨(せんこつ)、尾骨(びつい)3~6個の計約30個の脊椎から構成されています。
脊椎分離症は、ほぼ腰椎に起こるため、分離症といえば「腰椎分離症」を指すことが多く、5つの腰椎の中でも仙骨に近い、下位腰椎(特に上から数えて5番目の第5腰椎)に多く認めます。
脊椎には「椎弓(ついきゅう)」という弓状に飛び出た突起があります。椎弓は、上の脊椎と下の脊椎とをしっかり固定する上関節突起と下関節突起の間を橋渡ししており、脊椎にとって非常に重要な構造の一つです。この椎弓が分離した状態が、「脊椎分離症」です。
2.子供に多い分離症
子供の背骨はまだ柔らかいため、スポーツなどで過剰に負荷がかかると力学的に弱い部分がすることがあります。
腰痛を持つスポーツ選手を対象とした調査では、16~40%(研究によって差があります)が腰椎分離症であり、腰痛を持つ18歳以下の若者でも約16%に腰椎分離症を認めた、という報告があります。
さらに、腰を伸展させた時に痛みがあり、ほぼ毎日スポーツをしている10歳~18歳の若者では、なんと、約半数に腰椎分離症を認める結果となりました。
このことから、10~18歳の発育期に習慣的にスポーツを行っている子供は非常にリスクが高いことがわかります。
3.子供以外に分離症は起こるのか?
諸説ありますが、基本的に椎弓のみが外傷で損傷をうける可能性は低く、年齢とともに頻度が増加する傾向も認めていません。特に、骨がしっかり形作られる高校生以降での分離症発症は、非常にまれです。
高齢者では椎骨が前後にすべる「すべり症」と合併する、「分離すべり症」を認めることがあります。
3.遺伝との関係は?
腰椎分離症は家族内での発生例が多いため、遺伝的素因が一因と考えられています。
椎体や椎弓の形態異常、あるいは二分脊椎などの脊椎の病気を合併しているケースも見受けられ、兄弟姉妹で分離症を発症した例も多く報告されています。
こういった遺伝的、体質的な要素にスポーツによる過度の力学的負担が加わって疲労骨折が起こるのではないか、という説が有力です。
4.子供でのすべり症合併
すべり症とは、上下の脊椎が前後にずれる状態のことです。分離症によって起こる「分離すべり症」と、分離をともなわない「変性すべり症」に大きく分けられます。ここでは、分離すべり症についてお話しします。
上下の脊椎の間には椎間板(ついかんばん)という繊維とコラーゲンでできたクッションがあります。脊椎と椎間板の間には、成長軟骨が存在し、高校生頃までに硬い骨に置き換わります(骨化)。
子供の場合、分離症によって上下がぐらぐらで不安定になった骨を、柔らかい成長軟骨が支えきれずに上下の脊椎がずれてしまい、「分離すべり症」となります。
5.分離症をもった人が中高齢になったら?
分離症を持つ子供が中高齢になると、脊椎と脊椎との間のクッションの役割を果たす椎間板のコラーゲンが失われて椎間板が硬くなり、椎間板が変性することですべり症を合併することがあります。
すべり症合併例の多くは神経を圧迫して、腰痛と神経根刺激症状(しびれ、筋力低下)が出現します。
6.早めの診断・治療が大切
治療の基本は、手術を行わない保存療法です。保存法には2種類あり、分離した骨を再びくっつける「骨癒合(こつゆごう)」を目指す治療と、「疼痛コントロール」のための治療です。
発症早期であれば、運動の中止と分離症治療用のコルセットを用いることで、分離した部位の骨癒合(こつゆごう)が期待できます。通常数ヶ月~半年の治療が必要となります。
若年であるほど、成長軟骨が柔らかく、すべり症を合併しやすいため、進行度に関わらず、コルセットの治療を行われることが多いです。
しかし、激しい運動をしなければ無症状であることも多いため、受診したときには完全に分離しており、分離した部分が関節のようになる、「偽関節」の状態であることも多いのが現状です。この場合は、骨癒合は困難であるため、疼痛コントロールに主眼がおかれます。
病態が進行して痛みが強い場合やスポーツ活動を今後も継続するために、腰椎分離すべり症に対して脊椎固定術という手術が行われることがあります。こうなる前、つまり骨癒合が期待できる時期に、早めに診断、治療してあげることが重要なのです。
2015年11月25日 : 未分類
スポーツを行う子供にしばしば発症する腰椎(ようつい)分離症は、早めに診断し治療を受ければ分離した骨が再び癒合(ゆごう)して、完治する可能性が高い病気です。しかし、実際には病院に来たときにはすでに症状が進行しており、完治が難しいのが現状です。
今回は、子供が腰痛を訴えたら、どの病院に行くべきか、また、なぜ病院受診が必要なのかについてお話しします。
1.分離症の診断・治療ができる病院とは?
分離症の治療をうけるには、まず本当に分離症かをきちんと診断してくれる施設に行く必要があります。
分離症は、腰を反らせる動作(伸展)、前かがみになる動作(屈曲)で腰痛が出現するという特徴的な症状があり、発育期のスポーツ選手が腰を伸展させたときに痛みが生じた場合、約8割の人が分離症を認めたという報告もあります。
しかし、これはスポーツを行う若者に発症する腰椎椎間板ヘルニアにも見られる症状で、分離症全ての人がこの症状を示すわけではありません。そのため、確定診断には、レントゲン、CT、MRIといった画像検査が用いられます。そして、その結果を参考に、病気の進行度に応じた病期分類で評価を行い、治療方針を決定します。
CT、MRIが普及するようになり、分離症の正確な診断が可能となりましたが、未だにこれらの画像検査がなされずに「ただの腰痛」として見逃されているケースも多いと考えられています。
したがって、これらの検査ができる施設を受診することが必要です。CT、MRIは大きい病院にしか置いていないため、あらかじめインターネットや電話で確認することをおすすめします。
2.スポーツ専門の医師に診察してもらうには?
腰椎分離症はスポーツを習慣的に行う子供に多いことから、スポーツによる診断・治療に特化した日本整形外科学会認定スポーツ医に診察をしてもらうのが一番確実です。
日本整形外科学会のホームページから全国の日本整形外科学会認定スポーツ医を簡単に検索できます。そのほか、サイト内には整形外科疾患についての詳しい解説もありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
3.近くの病院?それとも遠方の有名な病院?
ここで注意をしたいのは、腰椎分離症と診断をうけた場合、治療は数ヶ月以上に及ぶことがあるということです。希望する先生が近医とは限りませんが、病院が遠方であればあるほど、治療を受ける子供や親の負担となるため、できるだけ定期的な受診ができる範囲で病院を探すことが大事です。
4.治療に応じた病院選び
分離症のどの時期においても、まずは手術を行わない保存療法が基本であり、コルセットによる体幹の固定や疼痛に関する薬物療法が行われます。しかし、分離症の治療の前に、専門医のもとで確実に分離症と診断してもらうことが大事です。
子供の成長期腰椎分離症では、発症早期であれば、数ヶ月~半年ほどのコルセット着用とスポーツの中止によって、分離した骨がくっつく骨癒合(こつゆごう)を期待できます。
一般的には、レントゲンやCTの画像で、分離部分の安定性や骨癒合の完成度を評価しながらコルセット治療を終了する時期を検討します。
一旦診断を受けて治療方針が決まれば、保存療法に関しては基本的にどの整形外科医でも対応可能です。遠方の病院を受診した場合は、先生と相談して、近くの整形外科を紹介してもらい、疼痛時など問題があったときにすぐに対応してもらえる病院をみつけておきましょう。
症状が進展して、分離すべり症となり下肢のしびれや筋力低下などの神経症状が出現している場合は、手術が選択されることが多いため、多少遠方であってもスポーツ整形外科専門医がいる病院がおすすめです。
5.そのほかの選択肢は?
整体やお灸を用いた治療など、インターネットには分離症に対するさまざまな治療方法が挙げられていますが、そのほとんどが、個人の経験談や治療談であり、エビデンスがはっきりしない情報も多く、内容を鵜呑みにしないことが大切です。
医療機関での治療は数ヶ月以上と長く、慢性的な痛みが残ることもあるため、思わず「この方法で治ります!」といった宣伝文句に飛びついてしまうかもしれません。もちろんそれで治った方もいるかもしれませんが、万人に効果がある方法とは限りません。
一方で、医療機関での治療は、これまでの医療情報や臨床研究結果に基づいた根拠のある治療を行うことを基本としています。分離症では、これまでに多くの臨床研究や、動物実験などが行われて病態のメカニズムや治療法が研究・検討されてきました。
研究が進むにつれて、今後、新しい事実が証明され、新規の治療が開発されるかもしれませんが、いずれにしてもエビデンスに基づいて医療行為が行われるため、個人的なサイトの情報よりは信頼性が高いと考えられます。
また、正確な診断をうけないまま、マッサージに通う、あるいは自己流で筋トレをすると、逆に腰の負担を増加させて症状を悪化させることもあります。
子供の将来を考えて、分離症を疑う場合は、まず適切な医療機関にかかることをおすすめします。
どこに行っても改善しなかった場合はてらだ鍼灸整骨院がお力になれるかもしれません。
0120−405−100